チャットボットの作り方を5つのステップで徹底解説
AIチャットボットの導入を検討し始めた方は「チャットボットはどうやって作ると成果が出るのか」と思案しているのではないでしょうか。今回はチャットボットの作り方を具体的に解説していきます。
チャットボットベンダーが提供する作成ツールを使えば、プログラミングがわからない方もたった5つのステップでチャットボットの構築が可能です。
この記事を読めば、チャットボットの導入から運用までの全てのステップを理解できますので、最後までご覧ください。
STEP 1 チャットボット導入の目的を決める
まず、チャットボットを導入する目的を明確にします。
目的を明確にすることで、チャットボット導入に携わる社内メンバーやベンダーの担当者と認識を共有することができ、目的に合ったチャットボットを導入することができるからです。
例えば、チャットボットの導入目的には以下のような例があります。
チャットボット導入の目的
- 社員から管理部門(人事・総務・経理など)に寄せられる問い合わせを減らしたい
- コールセンターへの入電数を削減したい
- 知見の属人化を防ぎ、社内の情報やノウハウを有効活用したい
- Webサイト上の情報を探しやすくして離脱率を改善し、顧客満足度を高めたい
このような目的を設定することで、その目的を達成するために、どんなチャットボットを導入すれば良いのか比較検討しやすくなります。
STEP 2 チャットボットベンダーの選定
チャットボットの目的が決まれば、どんなチャットボットを導入すべきかがわかります。自社開発も可能ではありますが、以下の自社開発とチャットボットベンダーの比較表をご覧いただくとわかるとおり、チャットボットベンダーを選定する方が費用対効果は高くなります。
| メリット | デメリット | |
|---|---|---|
| 自社開発 | 開発リソースの許す限り自由に開発ができる | チャットボットで効果を出すためのノウハウに乏しい |
| 自社システムと連携しやすい | メンテナンスも自社で行う必要あり | |
| ゼロからの開発のため導入まで時間がかかる | ||
| チャットボットベンダー | 導入までが早い | システム連携やカスタマイズの幅に限界がある |
チャットボットの作成、運用ノウハウがない企業にとって、自社開発はハードルが高くなりますので、チャットボット導入ではチャットボットベンダーを選ぶとよいでしょう。
また、チャットボットといっても「ルールベース型」の会話エンジンを使っている場合は、AIを搭載していません。チャットボット選定時には会話エンジンのAI搭載有無、さらに搭載しているAIの種類についても確認しておきましょう。チャットボットのAIについては以下の記事をご覧ください。
また、チャットボットベンダーはクラウドサービスを利用すれば、機能やセキュリティーのアップデートも自動で行われるうえ費用も安く、管理は非常に簡単です。当社の「サポートチャットボット」はクラウドサービスで提供しており、自社システムとの連携も可能です。
STEP 3 シナリオ(Q&Aデータ)を用意する
チャットボットのベンダーを選定できたら、今度はシナリオ(Q&Aデータ)を作成しましょう。チャットボットはQ&Aデータをベースに動くようになっています。WebサイトのFAQのデータや社内のマニュアルを元にして、フォーマットに沿ったエクセルデータを作成すればチャットボットの原型が出来上がります。
FAQのデータやマニュアルが社内にない場合でも、ベンダーによってはQ&Aデータの作成をサポートしてくれることがあります。当社の「サポートチャットボット」では、社内向け(人事・総務・経理財務・法務・情報システムなど)、社外向け(ECサイト、会員サービス、不動産、自治体)のQ&Aテンプレートも用意しており、さらに専任のカスタマーサクセスチームと相談しながら、フォーマットを作成できます。
サービスの詳細の資料はこちら

STEP 4 チャットボットを構築・テストする
Q&Aデータをもとにチャットボットの形にしていく初期構築に関しては、ベンダー側で設定する場合もあれば、自社でチャットボットを構築しなければならない場合もあります。自社で構築する場合は、導入したチャットボットの特徴や性能を十分に理解していないと、思ったような動作にならなかったり、構築に非常に時間がかかってしまうケースがあります。
チャットボットの初期構築は担当者の高度なノウハウが求められる作業で、良いチャットボットを作るうえでは非常に重要です。そのため、初期構築はチャットボットに精通した担当者が行うべきです。
初期構築が完了したら、公開前に実際にテストして正しい回答を返せるか、使いづらい箇所はないかを確認してみましょう。スムーズに求めている情報にたどり着けるか、いろいろな聞き方をしてみても、しっかりと回答を返せているかなど、 クリック形式、自由入力形式の両方で確認しましょう。回答精度が悪い箇所が見つかった場合は、設定を再度チューニングします。
当社では、チャットボット構築専任チームが STEP3で作成したシナリオをもとに高品質なチャットボットを構築代行しますので、高品質なチャットボットを短期間で作ることができます。チャットボットの作成や設定を構築専任チームが行いますので、ご自身で設定する手間がかかりません。公開までのテスト期間も専任チームがサポートしますので、公開後すぐに高いパフォーマンスを発揮することができます。
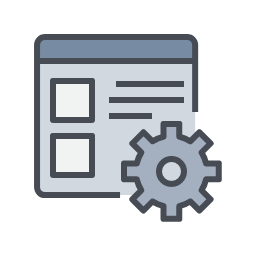
STEP 5 チャットボットの公開とブラッシュアップ
STEP4まですべて完了したらいよいよチャットボットを本番環境で公開します。その際、社内サポート利用の場合には、チャットボットを公開したことをアナウンスして認知度を向上させましょう。カスタマーサポート利用の場合もサイトにお知らせを出すなど、より使ってもらえるように工夫をすることが大切です。
その後は、日々蓄積するユーザーの利用データをもとにブラッシュアップを行い、よりニーズにあった精度の高いチャットボットにしていきましょう。 チャットボットの利用状況を直感的に把握でき、その後の改善にいかしやすいことも、チャットボットベンダーを選ぶ上で、重要なポイントのひとつです。
回答精度が悪い箇所が見つかった場合は、設定を再度チューニングします。当社の「サポートチャットボット」の場合は、公開までのテスト期間も専任チームがサポートしますので、公開後すぐに高いパフォーマンスを発揮することができます。
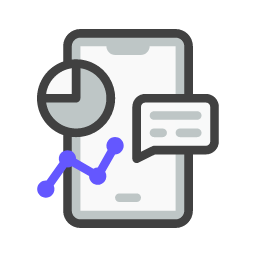
チャットボット公開後に成果を出すために見るべき3つのKPI
チャットボットで成果を出すためには、公開した後も回答できなかった質問や解決できなかった質問を分析してメンテナンスを続けていく必要があります。
チャットボットは導入して、運用していきながら業務効率を高めていかなくてはなりません。以下の3つのKPIに注力して運営していきましょう。
- ①ユーザー数とチャット数
- ②チャット返答率
- ③解決/未解決率(どれだけチャットボットで解決することができたのか?)
各KPIについては、以下の記事で詳しく解説しておりますので、あわせてご覧ください。
【法人向け】実際にチャットボットを作ってみたい方へ
ユーザーローカルの「サポートチャットボット」は法人向けクラウド型のチャットボットです。Webブラウザの管理画面にアクセスして手軽に設定することができ、チャットボットを平均1ヵ月〜3ヶ月という短期間で導入することができます。
「チャットボットを作ってみたら、どんな動きになるのか触ってみたい」「実際にチャットボットの作成を体験してみたい」そんなご担当者様向けに、期間限定で無料トライアルをご案内中です。ご興味お持ちいただける方は、以下よりお申し込みください。

